皆さんは花祭りをご存知ですか?
仏教の開祖、お釈迦様の生誕をお祝いする仏教行事です。
詳しくご存知ない方のために、花祭りの由来や使用される甘茶についてなどを詳しくご紹介します。
花祭りとは?灌仏会ってなんのこと?
お釈迦様の誕生日である4月8日、お釈迦様のお堂の周りに春の花をたくさん飾り付けます。その後甘茶をひしゃくですくい、お釈迦様の頭からかけてお祝いします。
この行事を花祭りといいますが、元々は灌仏会(かんぶつえ)と呼ばれていました。
呼び名が花祭りに変わったのは、明治時代以降だといわれています。
【お花祭り 妙光寺】
花祭りと白い象の関係は?
花祭りには、白い象を作って子供たちが引くこともあるようですが、それには由来があるのです。
お釈迦様の母、マーヤさんは白い象がおなかの中に入る夢を見て、お釈迦様を身ごもったと伝えられています。当時は白い象が夢の中に出てくるのは、尊い方が生まれる証と信じられていました。
そんな由来から、花祭りには白い象が登場するのですね。
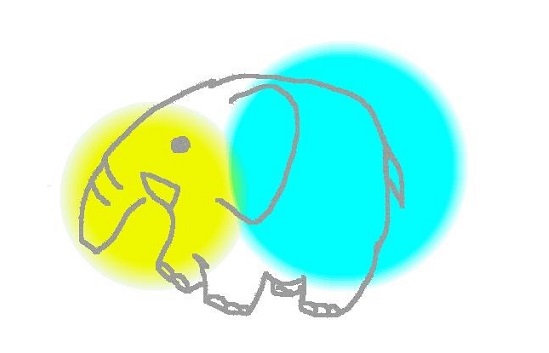
甘茶とは?
花祭りには甘茶が使用されますが、そもそも甘茶とは何なのでしょう?
その名前から、砂糖入りのお茶を想像されるかもしれませんが、そうではありません。
ユキノシタ科アジサイ属の甘茶という植物からつくられています。
甘茶の葉を収穫し、洗浄した後2日間天日干しにします。
その後乾燥した葉に水をかけ、気温25度の中で1日発酵させます。
葉をよく手もみして、乾燥させ、煎じれば甘茶の出来上がり。
後は日本茶などと同じ様にお茶を入れるだけ。
お茶なのでもちろんカロリーゼロですが、その名の通り味は甘いお茶です。
砂糖の500倍ほどの甘さがあるといわれており、糖尿病の方のための砂糖代わりとして使われることもあるようです。

甘茶に込められた意味とは?
花祭りに甘茶をお釈迦様の頭からかけるとご紹介しましたが、そもそも何故甘茶を頭からかけるのでしょう?
お釈迦様が誕生したとき、空からお釈迦様の生誕を祝うため、9匹の龍が甘い雨を降らせたといわれています。また、その雨はお釈迦様の産湯として使われたという説もあります。
花祭りではこの再現をするため、お釈迦様の頭から甘茶をかけているのです。

今回は毎年4月8日に行われる、花祭りをご紹介しました。
花祭りに参加する予定はない!という方は、甘茶だけでも楽しんでみてはいかがでしょうか?
カロリーゼロで甘く飲みやすいお茶ですので、ダイエット中の方にもおすすめですよ。


